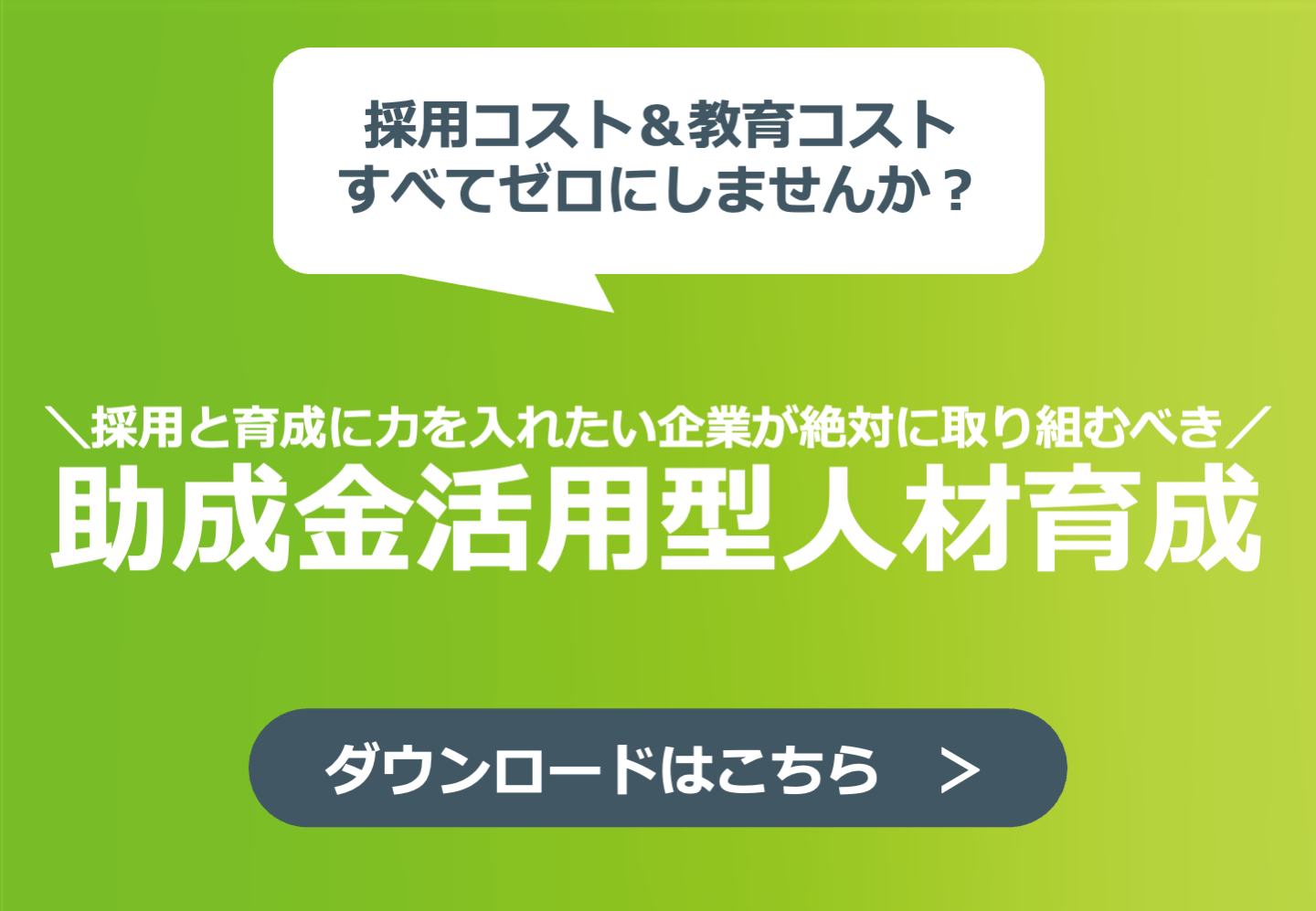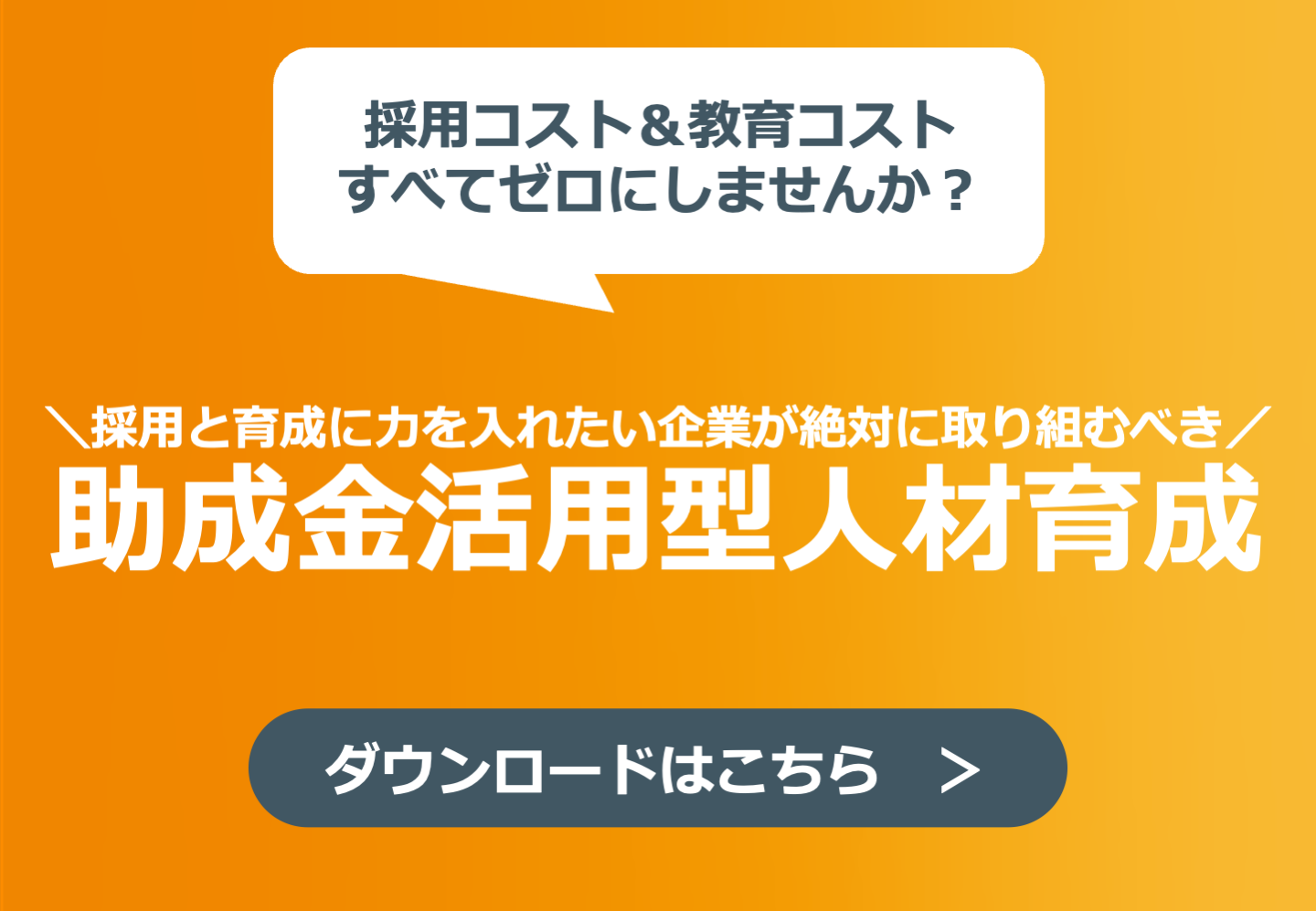ベンチャー企業とは?定義や意味、メリット、デメリット、向いている人の特徴などを紹介

「ベンチャー企業とはどんな会社?」
「ベンチャーで働くメリットは?」
「ベンチャーとスタートアップは違うの?」
ベンチャー企業は、社員一人ひとりの裁量権が大きく、自ら考えてビジネスをしたい人に向いています。ビジネスが成功して会社が成長すれば、ストックオプションがもらえる場合もあるので、大幅な年収アップの可能性がある点もベンチャー企業の魅力といえるでしょう。
しかし、ベンチャー企業は一般企業のように事業が安定していないケースも多く、デメリットもあります。また、働きかたも一般企業とは大きく異なるため、人によっては厳しい環境かもしれません。
そこで今回は、ベンチャー企業の定義や意味、メリット・デメリット、向いている人の特徴などを紹介します。
目次
ベンチャー企業とはどのような企業なのか
まずベンチャー企業がどのような企業なのか理解するために、概要と事業内容、待遇などについて解説します。
ベンチャー企業の定義や意味、特徴
ベンチャー企業とは、VC(ベンチャーキャピタル)などから出資を受けている企業、またベンチャー指定を受けている企業をさすことが一般的です。もともと「ベンチャー(venture)」とは「冒険・冒険的な企て、投機」といった意味で、革新的なビジネスモデルや技術によって、新たなビジネスを創出する発展途上の小規模、中小企業がベンチャー企業と呼ばれています。
ベンチャー企業の業務内容
ベンチャー企業の業務内容は、通常の企業と大きな違いはありません。ただし、社員数が少ない企業が多いため、1人あたりの業務量が多くなりがちです。また、企画から案件の実施、各種事務作業や経理業務、採用活動など、幅広い業務を任せられる点も、ベンチャー企業における業務内容の特徴といえるでしょう。そのため、社員1人あたりに与えられる裁量の幅も、一般的な企業に比べて広くなります。

ベンチャー企業の待遇
FASTGROW社の独自調査によると、ベンチャー企業の平均新卒給与は月収で26万5,855円、年収で382万6,400円とのことです。一方、令和2年の大卒平均は22万6,000万円であるため、一般企業よりは若干高めだといえるでしょう。また、一部上場などを果たせば、ストックオプションなどが社員に配布される可能性もある点も、ベンチャー企業の大きな特徴です。
ただし、ベンチャー企業の待遇は、企業規模や経営状況、事業フェーズなどによっても大きく異なります。例えば、アーリーフェースのベンチャー企業の場合、給与が安く激務、さらに福利厚生もあまり充実していないケースもあるため、個社ごとに違いがある点を認識しておきましょう。
参考:「ベンチャーは薄給」は本当か?~ベンチャー企業63社の新卒給与を徹底リサーチ~/FASTGROW
ベンチャー企業と混同されがちな企業や組織
ベンチャー企業と間違われることが多い、中小企業、スタートアップ、社内ベンチャーとの違いを解説します。
中小企業
中小企業とは、中小企業法によって定められた特定のガイドラインを満たす規模の企業をさします。例えば、サービス業の場合、資本金額5,000万円以下、従業員数100名以下の企業が中小企業です。そのため、中小企業でありつつベンチャー企業というケースも多いでしょう。
スタートアップ
スタートアップとは、新しいビジネスを急速に立ち上げイノベーションを起こすことによって、人々の生活を便利にしたり社会的課題を解決したりする企業です。スタートアップはベンチャー企業の一種ともいえますが、あくまでも新しいビジネスやビジネスモデルを推進するという点に違いがあります。また、スタートアップは企業規模で区別されないため、法人だけでなく個人事業主なども含まれるなど、企業形態が多種多様な点も特徴です。
社内ベンチャー
社内ベンチャーとは、事業を拡大するために企業内に設立される、新規ビジネスやアイディアの創出を目指す独立した組織のことです。大企業などが全社的に新規事業に取り組むとリスクが高くなるため、独立した組織を作ってスモールスタートしてリスク軽減につなげるケースが一般的でしょう。また、社内ベンチャーとしてはじめたビジネスが軌道に乗った際には、子会社として独立するケースも多くみられます。
ベンチャー企業で働くメリット・デメリット
ベンチャー企業には一般企業にはないメリットがある反面、デメリットもあります。代表的なものを紹介するので確認しておきましょう。
ベンチャー企業で働くメリット
ベンチャー企業では社員が複数の業務を担当することが多く、さまざまな経験を短期間に積むことができます。そのため、自分で考えてビジネスを回していく感覚を短期間で身につけられる点がメリットです。また、社員に与えられる裁量の幅が広いので、判断業務が多い点もベンチャー企業の特徴といえるでしょう。
さらに、ビジネスが軌道に乗って事業規模が拡大すれば、役員や経営者になれたり、ストックオプションがもらえたりするなど、一般企業に比べ年収が大幅に上がる可能性がある点はベンチャー企業ならではのメリットです。
ベンチャー企業で働くデメリット
ベンチャー企業は事業が成長段階であったり、発展途上だったりするケースが多いため、収入が不安定になる可能性が高い点がデメリットです。また、前述した通り、社員一人ひとりの業務負荷が高く激務になりがちで、残業も多い傾向にあります。
さらに、社内制度や福利厚生などが十分に整備されていないケースが多い点もベンチャー企業のデメリットだといえるでしょう。事業の成長や拡大に多くのリソースを割く必要があるため、事業が軌道に乗るまでは待遇面が改善されない可能性も否定できません。
ベンチャー企業に向いている人の特徴
ベンチャー企業は一般企業と異なる部分が多いため、人によって向き不向きがあります。以下のような特徴の人が、ベンチャー企業に向いているといえるでしょう。
向上心が強くチャレンジ精神が旺盛な人
ベンチャー企業は社員一人ひとりの裁量権が大きく、さまざまな仕事をする機会があるため早期スキルアップが期待できると説明しました。そのため、向上心が強くチャレンジ精神が旺盛な人には最適な環境といえるでしょう。
ベンチャー企業では短期間に多くの経験やスキルを取得できますので、自らを成長させてキャリアアップしたい人に向いていますが、高年収や福利厚生の充実を求める人には不向きかもしれません。

自らの意思でビジネスを進めたい人
社内のリソースが少ないベンチャー企業では、全社員がビジネスを自分事と捉え、自走する姿勢が求められます。そのため、仕事が与えられるのを待つのではなく、自らの意思でビジネスを進めたい人に適した環境です。
ベンチャー企業は一般企業に比べてビジネスが進むスピードが早いので、事業を成功させるために何が必要か自らリサーチや分析を行い、素早く行動に移す実行力が求められます。
世の中にない新しい商品やサービスを生み出したい人
ベンチャー企業は今までにないまったく新しいサービスや商品、ビジネスモデルを生み出し、社会課題の解決を目指します。そのため、自ら新規事業やサービスを考え、イノベーションを起こしたい人に向いているでしょう。
市場のニーズを敏感に読み取り、多くの人々の生活をより便利にする商品やサービスを検討してリリースすることは非常に大変ですが、やりがいのある仕事です。
将来的に企業や独立を検討している人
ベンチャー企業は経営者と社員の距離が近く、社員の視座が高くなりやすい環境といえます。そのため、一般企業では経営層や経営企画部門の社員しか携われない、企業経営に参画できる可能性が高い点もベンチャー企業の特徴です。
そのため、ビジネスを展開するための一連の流れを理解しやすく、将来的に独立して起業しようと考えている人にとっては、貴重な経験が積める環境といえるでしょう。
まとめ:イノベーションによって世の中を便利にするベンチャー企業
ベンチャー企業とは、ベンチャーキャピタルから出資を受けている企業や、ベンチャー指定を受けている企業です。まったく新しい商品やサービスを生み出し、我々の生活を便利にするベンチャー企業は、多くの経験やスキルが短期間で取得できるため、ビジネスパーソンには最適な環境といえます。業務量が多く大変な部分もありますが、ビジネスが軌道に乗れば大幅な年収アップが見込める点が魅力といえるでしょう。
しかし、濃密な経験が詰める反面、収入が安定しづらいなどリスクもあるので、就職、転職希望者は若い人が多い傾向にあります。また、ベンチャー向きの人材を採用しなければ、すぐに離職してしまう可能性が高いので、採用担当者は慎重に見定めなくてはいけません。
そこでおすすめしたいサービスが「HUB on」です。HUB onはAIも活用した革新的な人材サポートで採用と定着に貢献します。御社にマッチした理想的な人材の紹介、育成を実現し、社員の定着を実現することが可能です。
・HUB onのサポート内容
・活用メリット
・価格体系と採用コスト削減術
をまとめた資料が以下からダウンロードできますので、ぜひアクセスしてみてください。